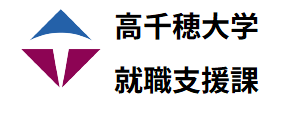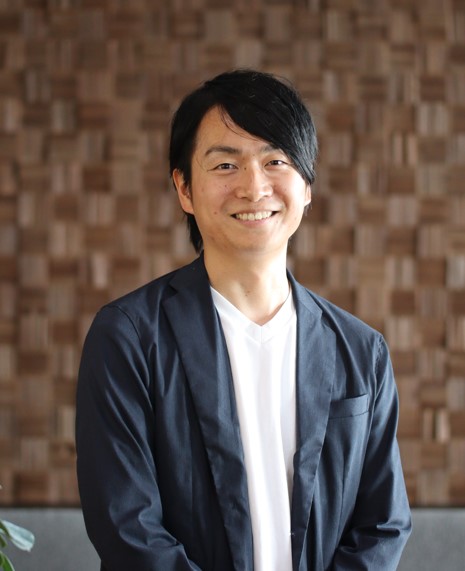
A・A さん
2014年3月 卒業
経営学部 経営学科
企業経営コース
仕事内容
中途採用業務およびHRBP(Human Resources Business Partner)を担当しています。中途採用においては、自社に必要な人材を獲得するため、ITエンジニアや営業職の人材要件定義から、募集、選考(見極めと惹きつけ)、内定まで一貫して行っています。
採用市場では、各企業が優秀な人材を獲得するための競争が激化しており、目標数を採用することは容易ではありません。そのため、タイムリーに人材を供給できるよう、応募者や関係者への迅速かつ柔軟な対応が求められる一方で、企業として本当にその人材を採用することが妥当かどうかを、さまざまな観点から慎重に見極めることが求められます。
HRBPとしては、事業責任者と連携し、課題を特定して必要な人事施策を提案することで、組織の事業成長に貢献することがミッションです。組織の事業成長という正解が見えづらい不確実な環境下では、多くの関係者を巻き込みながら、物事を中長期的な視点で広く、深く掘り下げて考えることが求められます。いずれも難しい課題ばかりですが、組織や個人の変化を実感できる、やりがいのある仕事です。
一日のスケジュール
※フレックス勤務およびテレワーク/出社のハイブリッドワーク体制のため、業務の都合に合わせて柔軟かつ自律的に業務を行うことが求められます。
| - | 勤務開始:タスクの計画や確認、会議や面接の準備、企画の検討や情報収集 |
| 9:00 | チャット・メール対応 |
| 10:00~17:00 | 社内外の会議や採用面接、社員面談、企画資料作成など |
| 17:30 | 勤務終了:子どもの幼稚園のお迎え~食事(残務があれば中抜け後、残業することもあります) |
現在の仕事・勤務先を選んだ理由
私は一度転職を経験し、中途入社です。学生時代のアルバイトや委員会活動、ゼミナール(経営心理)の経験を通じて、広義で「教育」や「組織」に興味を抱くようになり、1社目で人事部門に配属されました。その経験を活かし、現在まで人事のキャリアを歩んでいます。
現職に就いた決め手は、前職での採用経験が活かせること、職場のフラットな人間関係とコミュニケーション、そして個人の自律や挑戦が求められる風土が、自身の大切にしている価値観に近かったことです。
本学を選んだ理由
ゼミ活動に力を入れていたことが印象に残っています。少人数制のゼミでは、教授から丁寧な指導を受け、自分の興味に合わせて専門的な内容や、実際の社会課題を扱う実践的な取り組みを多く経験しました。このような経験が、自身の成長につながったと感じています。
また、よく言われていることかもしれませんが、高千穂大学の魅力は「学生、教授、事務局の方々の距離感が近く、アットホームな雰囲気」であることだと思います。小規模な大学だからこそ、学生一人一人に寄り添い、向き合ってくれる点は、大規模な大学にはない魅力です。
毎年学園祭の時期になると学校を訪れていますが、卒業から10年以上経過した今でも、教授や事務局の方々は私の名前と顔を覚えていてくださっています。私が在籍していた当時と比べると校舎は改装され、外観は大きく変わりましたが、学生に対する温かみや雰囲気は変わることがありません。青春時代を高千穂大学で過ごすことができて、本当に良かったと思います。
学生時代の思い出
印象に残っている活動は、ゼミナール(小林康一先生)での研究発表と学園祭実行委員長を務めたことです。いずれの活動も、共通の目標(ゴール)を描き、それに向かって協力して進める必要がありますが、これがなかなか思うようにいきませんでした。私自身も自己主張が強く(笑)、また、周りのメンバー同士がよくもめ事や争いを起こし、板挟みになることもしばしばありました。自分の役割や責任の重さを感じながらも、現実は思うようにいかず、さまざまなプレッシャーや不安を抱えながら活動していたことをよく覚えています。
当初、チームとしてはまったくまとまっていませんでしたが、少しずつお互いの理解が深まり、なんとか最後までやり遂げることができたと思います。振り返ると至らない点ばかりで、仲間に助けてもらうことも多かったのは事実ですが、嫌な現実から逃げずに最後までやり抜けたことは、(今後同様のことがあっても)きっと乗り越えられるだろうという自信や前向きな考え方につながり、現在の人事キャリアにも大きく影響を与えていると確信しています。

後輩へのメッセージ
大学時代、ゼミや委員会活動には全力投球していましたが、恥ずかしながら学業成績はあまり振るわず、機会があったにもかかわらず資格などにも挑戦できませんでした。その反省を踏まえて、社会人になってからは自分の興味のある分野を見つけ、国家資格を取得するなど学び直しています。私の周りには、在学中に大学に行く意義や意味を見出せず、「将来やりたいことがわからない」と悩み、途中で挫折してしまう人も見かけてきました。また、人事という職業柄、同じような就活生や応募者と接する機会も少なくありません。「大学の学び が将来どのように役立つのか」「何のために大学に行くのか」といった目的意識や計画性もちろん大事ですが、目の前の課題に真摯に向き合うことで、思いがけない出会いやチャンスを掴むこともあるかもしれません。私自身、今でも、人と組織の課題に向き合いながら、知らないことや未知の領域に向き合うことばかりです。ぜひみなさんも興味や関心の幅を広げ、教授や仲間とたくさんの学びを得てほしいと思います。

※本項に掲載されている内容は記事公開当時のものとなります。